算数の先取り学習は基本概念を覚えてその練習問題をやる流れでしたが、基本問題しかやらなかったため、考える練習がおろそかになってしまいます。そこで頼りにしたのがパズルでした。
今回は、息子が小学生時代に実際に使用したパズルをご紹介します。こちらはボードゲームと違って、絶版になっているものも少なくありません。現在でも購入可能な代替品があれば併せて載せていきます。
図形系パズル
タングラム

正方形を切り分けたピースを使って、様々な形を作り出すシルエットパズルです。自作も簡単で、問題はネット上にたくさんあります。これをやらない手はないでしょう。
オススメのやり方は、慣れた後は実物のピースを使わずに、頭の中だけで線を引きながら答えを出す方法です。実際に手を使っていると、偶然できてしまうこともあります。それを防ぐために頭の中でやります。熟練すれば、算数図形問題で補助線が見えやすくなる効果が期待できます。
アソートキューブMO

平面のシルエットパズルと立体パズルが楽しめます。立体の方をやることを想定して購入しました。立体は結構難しい上に、付属の問題集に答えが載っていないので、何度も挑戦できてお得?です。
パズルとしての難易度は高めです。根気がないと続かないでしょう。それだけに、このパズルの筋が良くなると、立体の認識レベルは向上するに違いありません。
現在でも販売しています。http://torito.jp/shopping/item.cgi?_assortcube-mo-2017
学研イージーキューブも同じ作者によるものです。
イージースフィア

一筆書きの要領ですべての球を取り去るパズルです。学研から発売されていましたが、現在は売られていないようです。おもしろいし独特のパズルなので再販希望です。
学研は2007年にアルゴを始め、ハッピードッグ、マティックス、トルーゴ、トリンカなどの「頭のよくなるゲーム」シリーズを立て続けに発売しました。(エンブレインというブランド名でした。)残念ながらアルゴを除い
た多くが絶版です。イージースフィアもその流れのパズルだったようです。(イージーキューブも同じ年の発売でした。こちらはまだ売られてます。)
論理系パズル
ロジックス

3色の○△□をヒントを頼りに配置していくパズルです。
タングラムなどのパズルを子供に好きにやらせると、適当に動かして偶然できることが少なくありません。その点、ヒントから答えはたった一つしか決まらないこのパズルは、論理とはどういうものかを理解する入門として優れています。
幼稚園年中〜小学校低学年までの子供には特にオススメです。うちの息子には年齢的にもう簡単になり過ぎていて、大した役には立ちませんでしたが、適齢なら是非とも、というパズルです。
しかし残念ながらこれは現在販売していません。販売元はやはり学研です。なんとか再販してもらえないでしょうか。自作は簡単なので、問題を作って出したいくらいなんですが、版権の問題等あるんでしょうね、たぶん。
ラッシュアワー

アメリカのシンクファン社から発売されていますが、考案者は日本人のパズルです。車を前後に動かして赤い車を外に出せば成功です。
付属の問題カードだけでもそこそこボリュームがありますが、物足りなければ拡張カードを買うことで長く遊べます。我が家では付属のものだけで十分でした。
アルゴ算数パズル

アルゴの問題集です。初級中級上級の3冊あります。初級の前半はルール確認のようなものですが、次第にパズル要素が濃くなってきて考え甲斐のある内容になってきます。
なかなかに問題集として優れているにも関わらず、現在3冊とも絶版になっています。アルゴゲームはまだ売っているのだから、このくらい再び販売できませんか?学研さん。1万円を超える価格で売り出している人もいますが、さすがにそこまでの価値があるとは思えません。でもそれほどのの価値を見出している人がいるわけですから、定番として売ればそこそこの需要は見込めるはずです。Kindle版でも良いので出してもらいたいですね。
宮本パズル
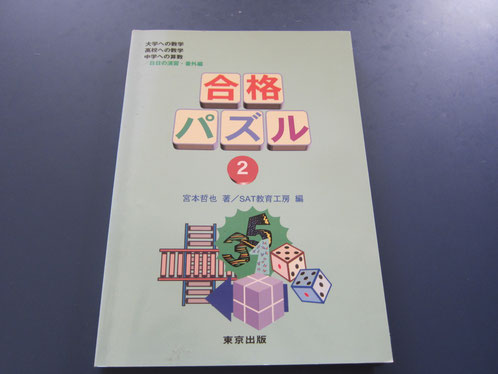
当時は現在のように宮本哲也氏のパズル本は豊富ではありませんでした。
私は宮本氏の著作「強育論」に感銘を受けた信奉者でしたから、今だったらこのシリーズをメインに勉強させたでしょう。この頃は著作が少なく、持っていたのはこの「合格パズル」シリーズだけでした。
あとは「中学への算数」のパズルコーナーを担当しておられたので、そちらに応募をよくさせてました。全問正解で名前が載るのはうれしかったようです。
現在の宮本パズルは「賢くなるパズル」シリーズとして学研から出ています。振り返ってみて気づきましたが、学研は良いものをたくさん出しているんだなと再確認しました。今後も頑張って欲しいですね。
なぞぺーシリーズ

こちらも現在のように充実していませんでした。出ていたのはこの4冊だけだったと思います。
あれから時が経ち、なぞペーシリーズの本ばかりでなく、花マル学習会もあちこちで見かけるほどに勢力を拡大しました。
なぞぺーシリーズ:http://www.soshisha.com/book_wadai/32nazope/2017.html
発売された時にはやや歯応えが無いものになっていました。もう少し早ければもっと役に立ったと思います。現在なら、宮本パズル同様に主力として働いてもらったことでしょう。
総括
上記のパズルは、比較的しっかりと取り組んだものです。それら以外にも、詰将棋やナンプレなどのペンシルパズルはちょこちょこやっていました。
だから、いつも何かしらの頭を使うものを、短時間でも毎日欠かさずやっていました。その習慣が高学年になってからの算数の難問を考える基礎となったのは間違いありません。
紹介したものでもそうでなくても、どんなものでも構わないので、是非ともパズルに取り組んで、考える習慣をつけておくことをお勧めします。
あと、学研さん、これからも頑張って!
コメントをお書きください